今回は「知識の伝達」に関する本の紹介です。
|
ジーン・レイヴ,エティエンヌ・ウェンガー著、佐伯胖訳『状況に埋め込まれた学習~正統的周辺参加』、産業図書、平成5年
|
内容
この間、いくらかの「知識の伝達」に関する本を読んだだめ、面白かった本を紹介します。ソーシャルワークとは直接関係がありませんが、私自身が取り組んでいるソーシャルワーカーの成長過程に関連する内容です。
あまりにも有名なこの本のタイトルは知っていましたが、今回ようやく手にする機会を持ちました。
正統的周辺参加とは何ぞや?「十全的参加」に向かうプロセスであり、「権力のもとであると同時に、無力さのもとであり、実践共同体間での結合と相互交流を喚起するとともに阻止もする」「正統的周辺性のこのあいまいな潜在力ことが、この概念が通常は関係しているとは認められないような諸関係の結び目に近づくためのかなめになる役割を反映している」(p.11)のだそうです。うーん、まだまだ私には咀嚼しきれません…。
そのなかにあり面白かったのは、第3章で産婆、仕立屋、操舵手、肉屋、断酒中のアルコール依存症者の5つの徒弟制の事例を用いて、正統的周辺参加者が実践共同体への十全的参加に向けた関わりを持つのかを展開している部分です。他領域の実情が分かり、興味深く読みました。
そして、本書の結論ともいえる部分が「忠実な模倣がその結果である場合でも、学習は決してたんなる知識の『伝達』とか、技能の『獲得』といったことで済む問題ではない。実践と結びついたアイデンティティ、知識や技能、さらには本人と共同体にとってのそれらの意義が問題にならないことはない」(p.103)という部分です。この一節は、自分の研究でも役立てることができるなと思いました。
目次
第1章 正統的周辺参加
第2章 実践、人、社会的世界
第3章 産婆、仕立屋、操舵手、肉屋、断酒中のアルコール依存症者
第4章 実践共同体における正統的周辺参加
第5章 結論
|
    |
生田久美子著『「わざ」から知る』、東京大学出版会、1987年
|
内容
先ほど、「徒弟制」という言葉が出てきましたが、日本の伝統芸道(茶道、華道、日本舞踊、落語等々)は師匠に弟子入りすることにより弟子が「わざ」を習得していきます。
では、「わざ」を習得するにはどうすればいいのか。「師匠の示す『形』の模倣、繰り返しを何年もつづけることによって、習熟の域に到達する」(p.14
)のです。しかし、ただ繰り返しを行うだけでなく「学習者は自らが権威として認める師匠の『形』を模倣し、繰り返すうちに、やがて、ある作品を成り立たせている要素的な『形』の意味を自ら納得したいという衝動に動かされていく。すなわち、『形』の意味の『解釈の努力』を始める」(p.37)のだそうです。ここでも、やはり習熟過程のなかで何らかの質的変化が伴っていることがみられます。
さて、2度目にこの本を読んだ時には、所々に伝統芸道とソーシャルワークの習得の違いをメモしながら読みました。それを見ると共通点と相違点があることがわかります。習得方法では、前者は「まねる、繰り返す」、後者は「自分でやってみて後に振り返り、再度行う」と書いてありました。
それらの違いを意識して読んでみるのも、面白いかもしれません。
目次
序章 型なし文化のなかで
1章 「わざ」の習得
2章 「形」より入りて、「形」より出る
3章 「間」をとる
4章
「わざ」世界への潜入
5章 「わざ」言語の役割
6章 「わざ」から見た知識
7章 結び―学校、生活、知識
補稿
なぜ、いま「わざ」か
|
    |
福島真人著『暗黙知の解剖~認知と社会のインターフェイス』、金子書房、2001年
|
内容
最後はやはり「暗黙知」について、語らないわけにはいかないでしょう。「暗黙知」はマイケル・ポラニーが提唱した概念であり、「我々は語ることができるより多くのことを知ることができる」(マイケル・ボラニー著『暗黙知の次元~言語から非言語へ』紀伊國屋書店、1980年、p.15)ことを意味します。
福島氏の本では、さまざまなルーティンのなかに潜む暗黙知を解読しています。しかしながら、氏も指摘するように、暗黙知を解明しようとする際のジレンマへの直面は悩ましいかぎりです。すなわち「暗黙知は、ある特定のタスク、あるいは特定の環境への習熟と密接に関係しているということは、前述した一連の例から見てもあきらかである。だが研究者にとっての障害は、まさにそれが言語化できないという点にある。というよりも、ポラニーの説明をより正確に繰り返せば、仮に言語化されても、それは実際に行われているタスクの複雑さをより十分に反映しきれないという点なのである」(p.46)。
さてさて、ソーシャルワーカーの「暗黙知」の解明はどこまで出来るのでしょうか…。暗中模索しながら、取り組んでいます。
目次
1章 ルーティンを観察する
2章 暗黙知を解読する
3章 システムを複数化する―徒弟制というモデル
4章
拡大する分業―歴史的パースペクティブ
5章 チームワークと認知
6章 「現場」と学習の構造
|
    |
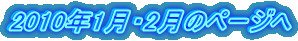
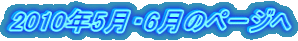
|
|
|

